こんにちは!
このブログでは、アラフォーのビジネスパーソンに向けて、本の学びを共有しています。
本日は『だから僕たちは、組織を変えていける やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた』 (斉藤 徹 著)の紹介です。

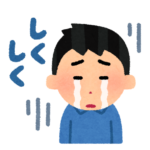
会社の人間関係がしんどい・・・
職場のチームの雰囲気が良くない・・・
あなたたのそんな悩みを解決します。
- 『だから僕たちは、組織を変えていける やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた』の要約と所感
著者の斉藤徹さんは起業家、経営者、教育者、研究者という多様な経歴を活かして、大学教授として教鞭を執られている。企業向けの講演実績は数百社に及び、組織論、企業論に関する著書も多いです。
本書には、職場や組織でメンバーが生き生きと働くためのチーム作りのためのメソッドやマインドセットが多岐にわたり纏められています。情報公開し過ぎるとネタバレになるので、私の意見を交えながら、要点を絞って伝えしたいと思います。
それでは、早速いきましょう!
心理的安全性
最近「心理的安全性」という言葉をよく耳にしますが、そもそもなぜ心理的安全性が必要なんでしょうか。
私の答えは、「主体的、能動的に働ける職場環境が、社員の活力になるから」だと思っています。
高度経済成長期は、企業の経営層や管理職からトップダウンで降りてくる指示を、愚直に、効率性をもって体現すれば経済が回っていました。
人口も増えていましたし、モノが売れる時代で「大量生産、大量消費」の市場原理に基づき、会社員のキャリアも「年功序列、終身雇用」で安定的に稼げる仕組みが出来上がっていました。
でも、そんな時代も今は昔。バブルも崩壊し、モノは溢れ、「皆と同じことを同じように行い、同じような人生を過ごす」という価値観は消え去り、政治・経済・社会・技術のグローバル化と多様性が浸透しました。
またウクライナ戦争や中東戦争、地球温暖化の加速等、世の中の不確実性が大きくなる中で、「誰かがやってくれる」「誰かの指示を待つ」という受動的な行動、人生指針では、我々は今後生き残れなくなると思っています。
求められているのは、
「一人一人が自らの意思を持って行動を起こし、今までにない新たな価値観を創出しながら、主体的・能動的に生きていく」
ことだと思います。
ですので、心理的安全性が企業や社会でうたわれているのは、必然なんだと思っています。
組織は「統制」から「自走」へ

では、そんな世の中でどんな組織が「あるべき姿」なんでしょうか。
それは、「自走する組織」だと思います。
効率性が重視され、組織が管理・統制されることに意義が見出されていた時代は過ぎ去りました。
一人一人の個性と価値観がきちんと尊重され、企業の理念やビジョンに基づいて新たな価値やサービスを生み出す文化や仕組みづくりが必須になっています。
売上などの定量的な目標が最優先となり、「在り方」や「やり方」等のプロセス、定性的な状態を”ないがしろ”にすることは、社員のやりがいや幸福度を押し下げてしまうことに繋がってしまいます。
職場の雰囲気も悪くなる一方で、そうなると、余計にコミュニケーションも取りづらくなって、更に数字も落ちてくる、という悪循環に陥るでしょう。
「数字」より先に「関係性」を築くことが組織や企業の存続と繁栄に繋がるんだと思います。
トップダウンで統制・管理されるのではなく、ボトムアップで自らが率先して動いていくスタイルがメンバーの「やりがい」や「生きがい」に繋がると思います。
リーダーが強がりの仮面を外す

そのような組織を築く中で、リーダーの役割は非常に重要になります。
では理想のリーダー像とはなんでしょうか?
非の打ち所がないサイボーグのような人でしょうか。
私の答えは「チームの成果が最大化されるように、所属するメンバーが働きやすい環境を自ら作れる人」だと思っています。
なぜなら、過去の上司像は、部下の上に立つものとして「強くあらねばならない」という既成概念が先行し、組織が硬直しやすくなっていたからです。
リーダーはメンバーにマウントを取ることが目的でないです。チームのメンバーが気持ちよく前向きで主体性をもって動き続けられるようにしてあげる事が、今は必要です。
このことを肝に銘じておくべきだと思います。
たったひとりから影響の輪は広がる

本書でインプットして納得するだけでは、何の意味も持たないと思います。それは本書を読んでいないのと同じだと。
大事なのは「とにかくやってみる」こと。
行動が全てです。それはまず学んだ事を同僚や他の部署の人と立ち話でも共有してみるのも一つです。
最初は「こいつ何言ってるの?」「そんなきれいごと言ってできるわけないやん。」と一蹴されるでしょう。
勝負はそこからです。
他人を変えることは本当に骨の折れる作業で、ましてや会社組織を変えていこうと途方もない時間と労力がかかります。
でもそれだけ”やりがい”があると言ってもいいでしょう。
大事なのは「論破でなく、共感や理解を得ること」です。論破で相手を打ち負かしても、相手は行動してくれません。
仲間を増やすことに重きを置きましょう。
所感

まさに自分の会社や職場が心理的安全性の著しい低下がみられ、若手社員の離職が進んでいる最中でしたので、
全く他人事に思えず、気づきが本当に多く得られた本書となりました。
そして最近よく聞かれる「パーパス」は何のためにあるのかを知る契機にもなりました。
結局は組織が主体的に自走していくためにはどうすれば良いかを考えて実行し続けることが大切で、
正解はないので走りながら最適解を見つけていくしかないと思います。
会社を一人の人間として生き物として考える。
色々と考えされた一冊となりました。
我々ができることは、一人でもまず始めること。
行動を続ければ、必ず何かが起こるし、逆に何かが起こらないと、何も変わらないということになる。
さぁ、始めましょう。




コメント